四季折々の佇まいを見せる海蔵川の川面に、今年も間もなく、桜の花が美しく映える季節を迎えます。春の到来が待たれる本日、6年生129名が卒業の日を迎えました。
保護者の皆様、お子様が小学校6年間の教育を無事おえられましたこと、心よりお喜びいたします。日々の子育ての葛藤の中、常に温かい御慈愛を注いでこられたことに篤く敬意を表し、また、本校教育へのご理解とご協力に深く感謝申し上げます。
本日、お招きすることができなかった地域等関係の皆様方に、この場をお借りしてご報告と御礼を申し上げます。なお、本日の式辞の一部を下に掲載させていただきました。


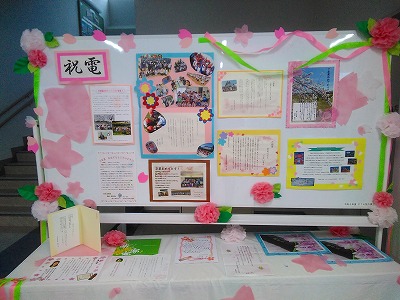


【式辞(抄)】
卒業生の皆さん、卒業おめでとう。皆さんは平成から令和、旧校舎から仮設校舎、そして桜色に輝く新校舎へと、まさに激流を経て本日を迎えました。特にこの二年、臨時休校もあり、遠足や運動会など楽しみな学校行事が自粛・制限を余儀なくされました。
しかし、皆さんは、常に明るく、前向きに、直向きに、学校生活を送りました。例えば、集団登校や仲よし活動・遠足などでは、低学年や中学年の子たちを明るく励まし、優しくリードしてくれました。また、二十分休みなどに運動場で遊んでいて予鈴がなると、「さー」と駆け足で教室へと戻る規律正しさ、そんな海蔵小学校のよき伝統を見事に引き継いでくれたことに感謝し、皆さんを誇りに思います。
卒業に際し、皆さんに、次の詩を贈りたいと思います。
「わたしは小さいとき、おやつのお菓子が弟より大きくないとおこった。地団駄踏んで泣いたこともある。わたしが世界のすべてであった。やがてわたしは、弟もわたしと同じように、大きいお菓子をほしがっていることが、わかってきた。わたしはけんかしながらも、同じように分けることをおぼえた。弟といっしょにお菓子を食べると、お菓子の分量はへったが、なんとなく楽しい。こうして、わたしの中へ弟がはいってきた。中略」
この詩の続きには、忙しそうに働いている家族を見ても平気だったわたしが、『わたしも手伝おうか』と言えるようになったことや、教室で教え合ったり助け合ったりして勉強することを覚え、「わたしの中へ、家族や友だちが入ってきた」ということが書かれています。
更に、こんな一節があります。
「わたしは社会科を勉強しながら、数字やグラフを一生けんめい暗記した。日本が生産力で世界第何位と聞くと、ただそれだけで、むねを張って喜んでいた。やがてこうした数字やグラフの背後には、ひたいに汗して働く人々のいることを考えるようになった。こういう人々がすべてしあわせにならねば、日本の国はいばれないと思うようになった。以下略」
この詩は、「わたしはひろがる」という題名です。皆さんの世界もこの六年間で、家から学校、地域、また、授業で学んだ広大な範囲へと広がっていったことと思います。学ぶことの意味はそこにあります。
今日、声に出しては歌えなかった校歌の誠実・勤勉の言葉を胸に、人を尊敬し、人に感謝することを忘れないでいてください。そして、これから出会うたくさんの人と豊かに交わり、目の前に広がる世界を逞しく切り拓いてくれることを願い、餞の言葉とします。
(詩:「わたしはひろがる(岸武雄)」から一部引用)