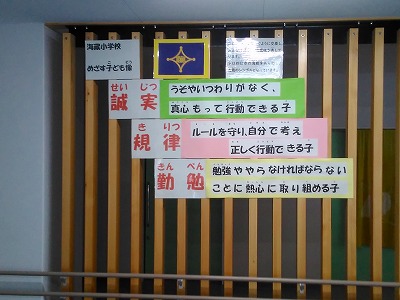4年生の算数では、やや複雑な図形の面積の求め方に挑戦していました。子どもたちは何通りもの方法を追究しようとしていました。後半、次の課題として手裏剣のような大変複雑な図形が提示されるとさらにやる気を高めていました。


6年生外国語では、黒板・スクーリーン・タブレットをつかって情報のインプット・アウトプットを繰り返しながら外国人派遣英語教師を交えて異言語でコミュニケーションを図るという、アクティブでハイブリットな学びが見られました。

5年体育「大縄跳び」のようすです。縄を回す回転が速いので写真には写せませんでした。ジャンプ力も持久力もさすが高学年です。大縄跳びは、息苦しくならないようにマスクをつけはずししながら、間隔にも気を付けて取り組んでいます。

人権擁護委員さんを迎えての2年生人権教室の様子です。4人の小学生の絵を見て、それぞれ男の子か女の子かをあてっこするゲームから始まりました。この活動を通じて性別は外見だけでは決められないことに気付いていきました。

学ぶ姿は一朝一夕に出来上がるものではなく、教師と子どもたちとの関係の中で次第に紡がれていくものと感じます。コロナ禍のもと、教室を「居場所」「絆」づくりの場として、心の距離を縮める授業づくりを進めていきたいと考えています。