3日(水)4日(木)に県立高校前期選抜が行われました。
面接や作文、学力検査など、高校や課によって選抜方法は違います。
昨日行われた学力検査の問題が
三重県教育委員会のHPに掲載されていますので、
3年生の皆さんはもちろん、1・2年生の皆さんもぜひ見て、そしてやってみてください。
この中から数学の問題を何問か取り上げます。
1・2年生で学習した範囲の問題ばかりですので、皆さん、挑戦してみてください。
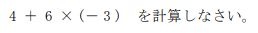
正の数・負の数の問題です。
計算の順序を間違えないことが大切ですね。
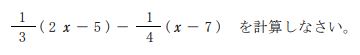
分数を含んだ文字の指揮の計算です。
通分する時、かっこをはずす時の符号にミスが起こりやすいですね。
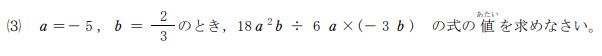
それぞれの値を代入してから計算するよりも、
式を簡単にしてから代入したほうが、ミスが減り、そして時間も節約できますね。
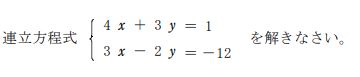
連立方程式です。
これは、1年生では学習していないので、ちょっと無理ですが、
2年生にはスラスラと解いてほしい問題です。
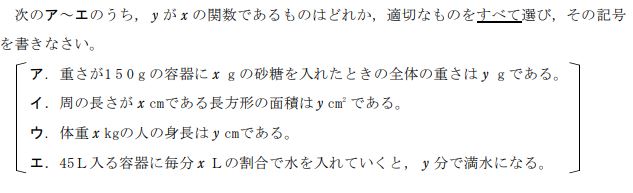
関数について、理解しているかどうかを確認する問題です。
教科書には、
「もとなって変わる2つの変数X、Yがあって、
Xの値を決めると、それに対応して、Yの値がただ1つに決まるとき、
YはXの関数である」と書かれています。
Xの値を1つ決めると、Yの値が1つに決まるのを選べばOKですね。
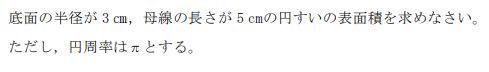
円すいの表面積を求める問題です。
簡単な展開図をかいて、わかっている長さを書き込んでいくと
側面のおうぎ型の中心角(円の何分のいくつか)がわかってきます。
それを使って、おうぎ形の面積を求めます。
底面の円の面積を足し忘れないようにしましょう。
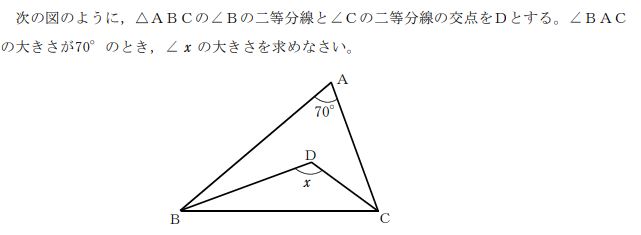
2年生の内容ですが、三角形の内角の和が180度であることが分かっていれば解ける問題です。
等しい角に〇や✖などを書きこんでいくと、わかりやすくなります。
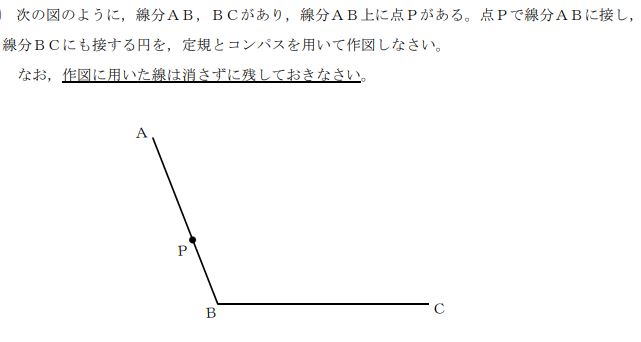
作図自体は、
「直線上の1点を通る垂線の作図」と「角の二等分線の作図」ができれば、求められます。
作図の問題ですので1年生の範囲ですが、
円や円の接線の性質を理解していないと解けない問題です。
接線については忘れがちですので、よく思い出しておきましょう。
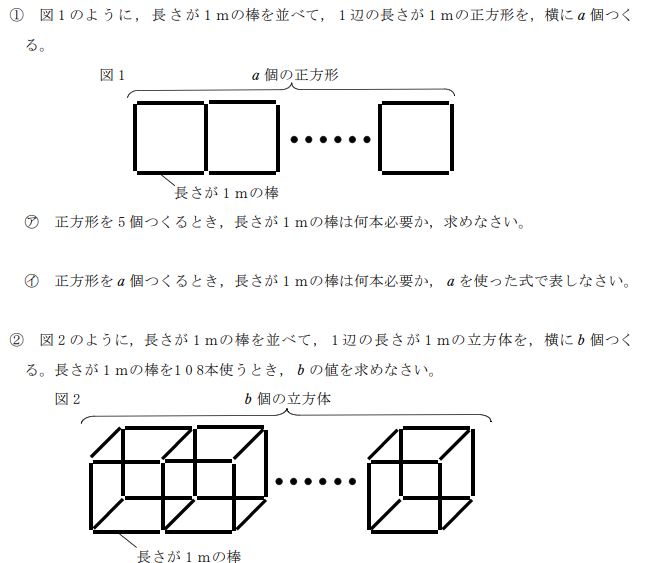
文章を読んで問題を理解し、規則性を見つけ、それを手掛かりに条件に合う場合を求める問題です。
正方形を並べていく問題の場合は、いろいろな考え方がありますが、
1本の縦棒に͡、3本のコの字型の棒を加えていくと考えるがシンプルでしょう。
正方形が1個のときは 1+3(本)
2個の時は、1+3×2(本)
3個の時は、1+3×3(本)
表を使ったり、小さい値から順に考えていくと、規則性が見やすくなってきます。
立方体の問題は正方形の問題を発展させているだけで、同じように考えたら関係が見えてきませんか?
何問かを取り上げました。
わからなかったり、疑問に思ったことがあったら、数学の先生に聞いてください。
教頭先生でもいいですよ。
また、他の教科の問題にもチャレンジしてみましょう。
数学に限らず、学力検査は、3年生の内容だけが出題されるわけではありません。
毎日の授業が大切です。
授業内容を忘れないようにするためには、復習が大事です。
コツコツと積み重ねていきましょう。