8月6日、7日の2日間に渡って浜松市で開催された
第37回東海地区学校図書館研究大会に提案校として参加してきました。初日の6日は現在の学校図書館の課題やより素晴らしい学校図書館にしていくためにどうすればよいのかという講演を聴きました。
また、学校図書館におすすめの本や読み聞かせ用の適したいろいろな本の展示を見て、新たな知識も得ましたので、2学期にはまた新たな本を入手して、担任や国語科による「読み聞かせ」もどんどんやっていこうと思います。

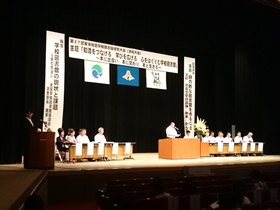
2日目は分科会に分かれての研究討議でした。私(味村)の参加した分科会は「学校図書館の学習情報センターとしての活用」というテーマ。発表する学校はさすがに優れたとりくみを行っています。聞いていてたくさんの刺激を受けるとともに、港中でもこれは活用できるといういくつかのアイデアも得ました。
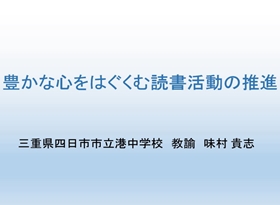

午後のトップが港中学校の発表。三重県の中学校でただ一校の発表なので、さすがに緊張と責任を感じましたが、これまで港中のみんなと一緒にいろいろな活動を頑張ってきたことを頭に浮かべつつ、胸を張ってしっかり発表してきました。
読み聞かせや本の紹介、ブックバイキングやブックトーク、そして1分間スピーチなど、昨年から港中学校で頑張っていることを一通り発表しましたが、テーマが「学校図書館の学習情報センターとしての活用」ですので、パソコン室と図書室の連携利用についてを中心に話しました。内容としては、調べ学習と発表活動。分かりやすく説明するために3年生がこの2年半にとりくんできた「港地区調べ」「職業調べ」「高校調べ」「人権総合学習」「社会見学や修学旅行とその発表会」など、教科と連携して主に総合の時間にポスターセッションやプレゼンテーションにとりくんできた流れを写真で示しながら発表しました。
港中学校のようにパソコン室と図書室が「繋がっている」図書室は、やはり珍しいようで、そういう利用しやすい環境をとてもうらやましいという感想をたくさんもらいました。また、他校の様々なとりくみや生徒の発表、まとめ活動の様子を見ていて、港中学校でやってきている様々な発表活動のとりくみは、どこと比べても劣ることがない素晴らしいとりくみで意義のある活動だと改めて思いました。同時に、これに満足することなく、さらに港中学校の生徒の力を伸ばしていくために、現在の活動を工夫し、新たなものを取り入れ、よりよいものにしていきたいと感じました。
